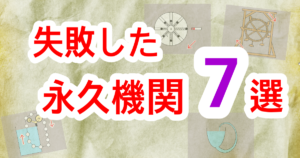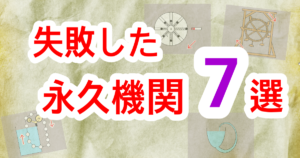これは永久機関かも?
と思ってしまう現象&仕組みはいくつか存在します。
永久機関は実現不可能なので、永久機関ではありませんが
- 水飲み鳥(平和鳥)
- 自転&公転運動
- 時間結晶(タイムクリスタル)
↑上記の3つは、理論や仕組みを説明してくれないと永久機関に見えてしまうかもしれません。
では、永久機関に見えるけど永久機関ではない現象&仕組みとは何か?
 パラバース博士
パラバース博士今回は、一見すると永久機関に見えてしまうエセ永久機関✖️3をご紹介します。
そもそも「永久機関」の定義とは?
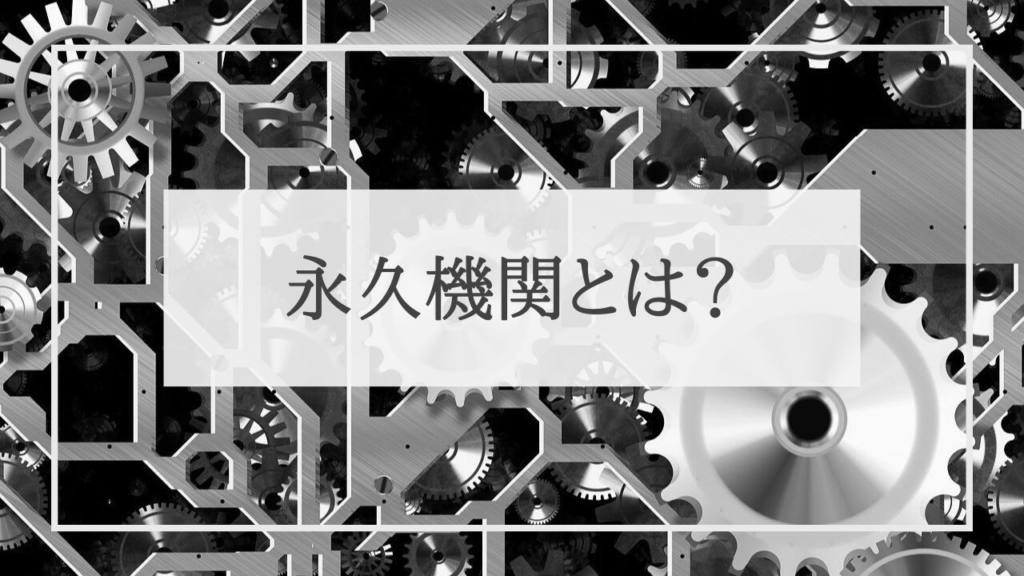
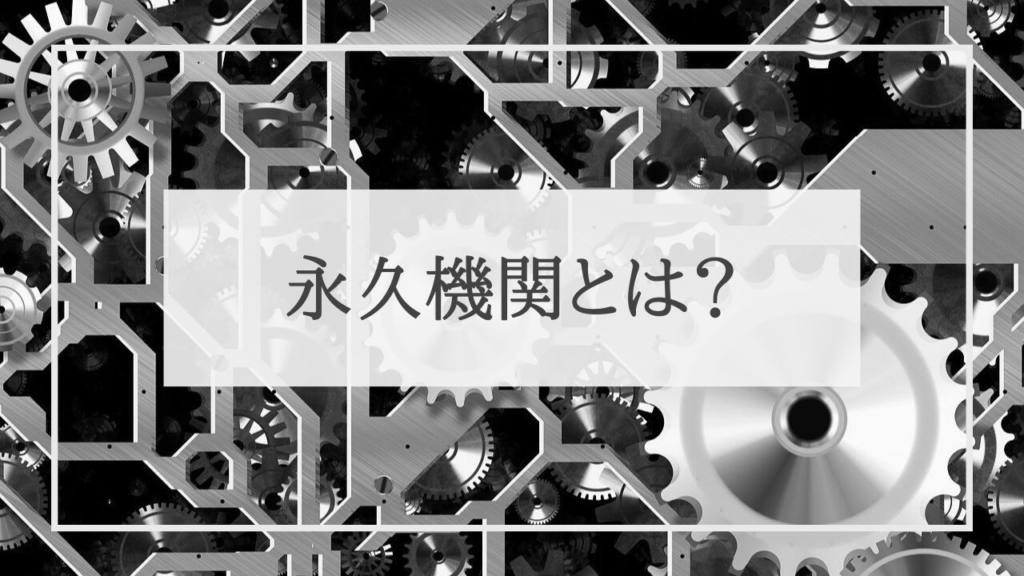



永久機関と呼べる機関&装置になるには、2つの条件を満たす必要があります。
- 外部のエネルギーに頼らず永久に動き続ける
- 動き続けながら他のエネルギーに変換し続ける
永久に動くだけでは永久機関にならない
例として、車輪を回転させるとそのまま永久に回転し続ける「永久回転輪」があるとします。
車輪が永久に回転し続ければ永久機関に見えてしまうかもしれませんが、摩擦抵抗なしで回り続けてもそれは永久機関と呼べないのです。
永久機関になるには、回転する車輪が外部のエネルギーに頼らず回転速度を増したり、他のエネルギーに変換できた後も回り続ける必要があるのです。



「物理学における仕事」をし続けると、永久機関と呼べる機関&装置になります。
「物理学における仕事」はちょっと難しいので説明を省きます。
永久機関に近い現象&仕組みとは?





紹介する現象&仕組みはこちらです。
永久機関に近い現象&仕組み✖️3
- 水飲み鳥(平和鳥)
- 自転&公転運動
- 時間結晶(タイムクリスタル)
水飲み鳥(平和鳥)
水飲み鳥(平和鳥)は、クチバシが水に浸く&起き上がるの動作を繰り返すおもちゃです。
同じ動作を反復し続けるので、一見すると永久機関に見えてしまいます。
しかし、クチバシを濡らす&蒸発を繰り返すとコップの水が減って行き、コップの水が無くなると水飲み鳥は機能しなくなるので、永久機関ではありません。
また「水の蒸発」は外部からのエネルギーに頼っているため、その観点からも水飲み鳥は永久機関ではないのです。
天体の公転
公転運動とは?
ある天体(星)が、ある天体の周りを回り続ける事を公転と呼びます。
私たちが住む地球も太陽を公転していて、地球が太陽を1周するまでの公転周期(期間)は365日です。
天体の公転は、大昔から一定の周期で繰り返している事から、一見すると永久機関に見えてしまいます。
しかし、公転は宇宙空間には摩擦がないから動き続けているだけで
- 動いているだけ
- 他のエネルギーに変換できていない
↑これでは、物理学における仕事をしていない状態なので永久機関と呼べないのです。
時間結晶(タイムクリスタル)
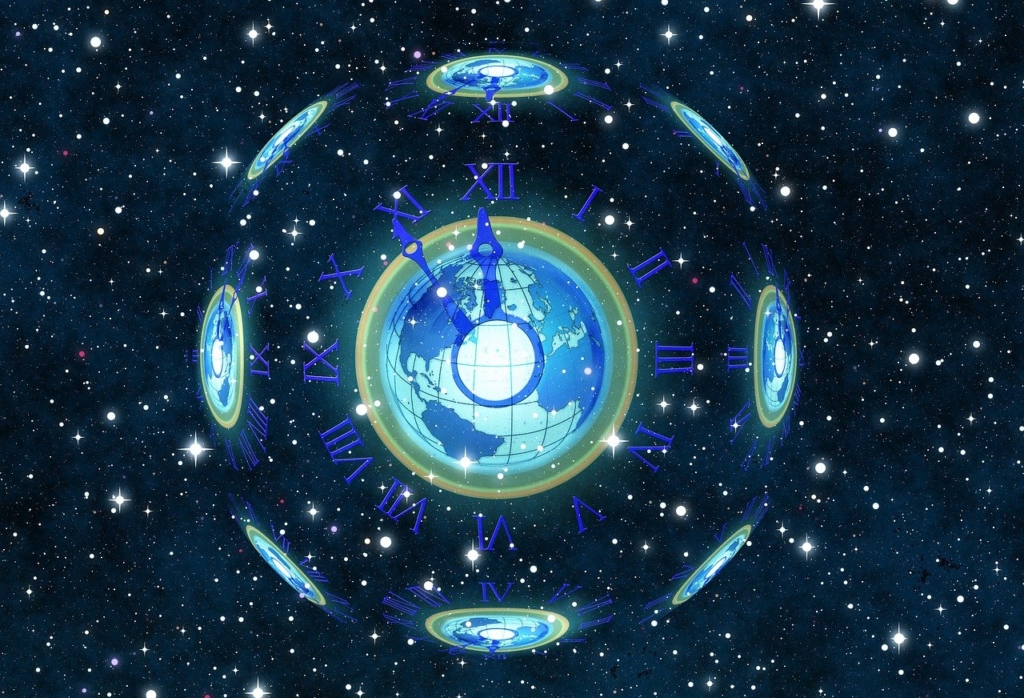
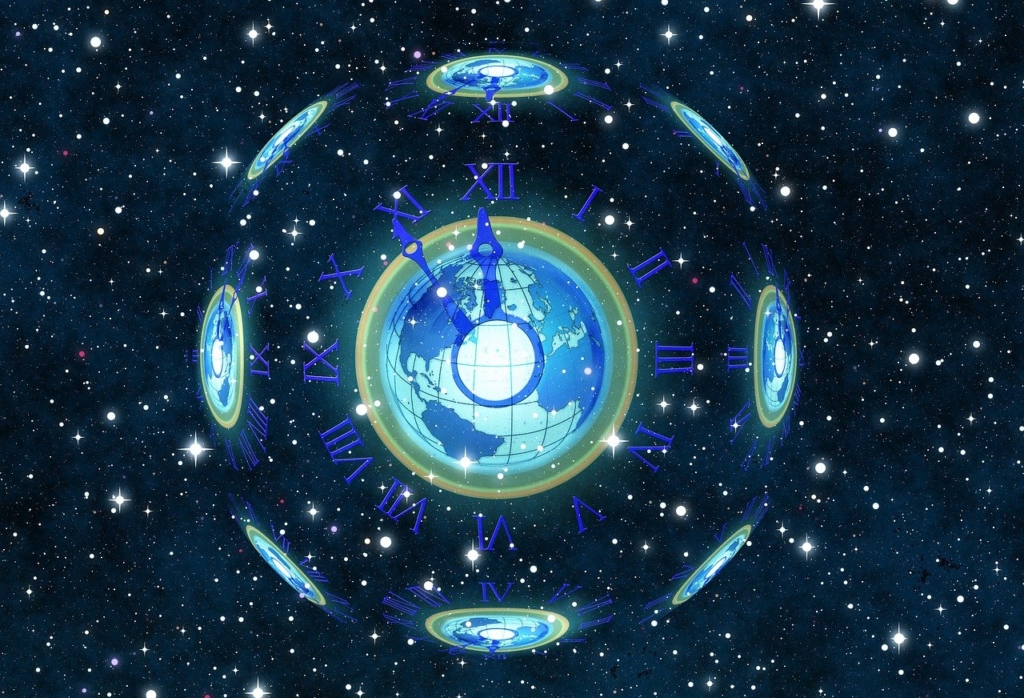
「時間結晶」とは、機関や仕組みではなく
- ドライアイス=個体
- 50℃の水=液体
- 〇〇=時間結晶
↑「状態」を表していて、気体、液体、個体、プラズマに次ぐ「全く新しい物質の形態」と考えられています。
時間結晶は、ある時刻で止まっていた物体が、動く&止まるの動作を繰り返す状態が確認されました。
物体が一定のリズムで振動し続ける事から、永久機関に近いと言われます。
しかし、エネルギーが動く&止まるの動作を繰り返しても物体の総エネルギーは変わらないので、時間結晶はあり得ない、存在しないとの否定意見もあります。
まとめ



永久機関に見えてしまう現象&仕組みは、結局外部からのエネルギーに頼っているので、永久機関になっていないのです。



やはり、永遠のエネルギーはあり得ないんですね。



もし「永久機関かな?」と思う物を発見したら、ググってみてはいかがでしょうか?



なぜ、永久機関ではないのか?その理由や仕組みを知るだけで面白いはずです。